ヒマつぶし情報
2022.11.17
ゲスの極み乙女・川谷絵音 音楽とNFTの可能性を語るトークライブを開催 「NFTかリアルか」テーマのトークライブ開催
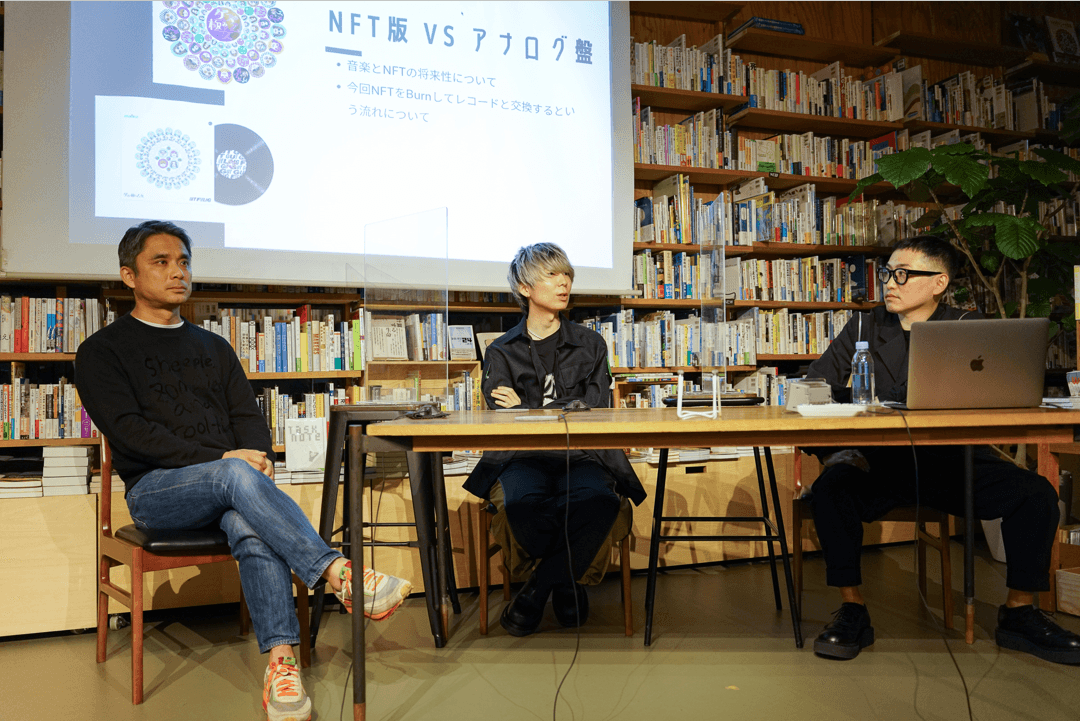
今年5月にバンド結成10周年を迎えたバンド、ゲスの極み乙女。7月に初となるNFT作品「Maru」(読み:マル、以下「Maru」)を発表しましたが、実はいま、「ワーナーミュージック・ジャパン」および、NFTの取引サービスを手がける「KLKTN」と同作品を通じて“社会実験”を行っています。
その内容は、同作品のホルダーに対し、Maruが保有するNFTを「バーンする(Burn)=燃やす」ことを条件に、今回のプロジェクトのために書き下ろされた楽曲「Gut Feeling」が収録された一点もののレコードへの引き換えを可能とするというもの。
そんななか、10月19日に「NFT版かリアル版か?音楽とNFTの価値を問うオフラインイベント」が東京・下北沢の本屋「B&B」で開催されました。同バンドボーカルギターの川谷絵音氏をはじめ、増井健仁氏(ワーナーミュージック・ジャパン エクゼクティブ・チーフプロデューサー)、岩瀬大輔氏(KLKTN CEO)が登壇。「Maru」の制作に至った経緯や、音楽業界におけるNFTの可能性について語ってくれました。
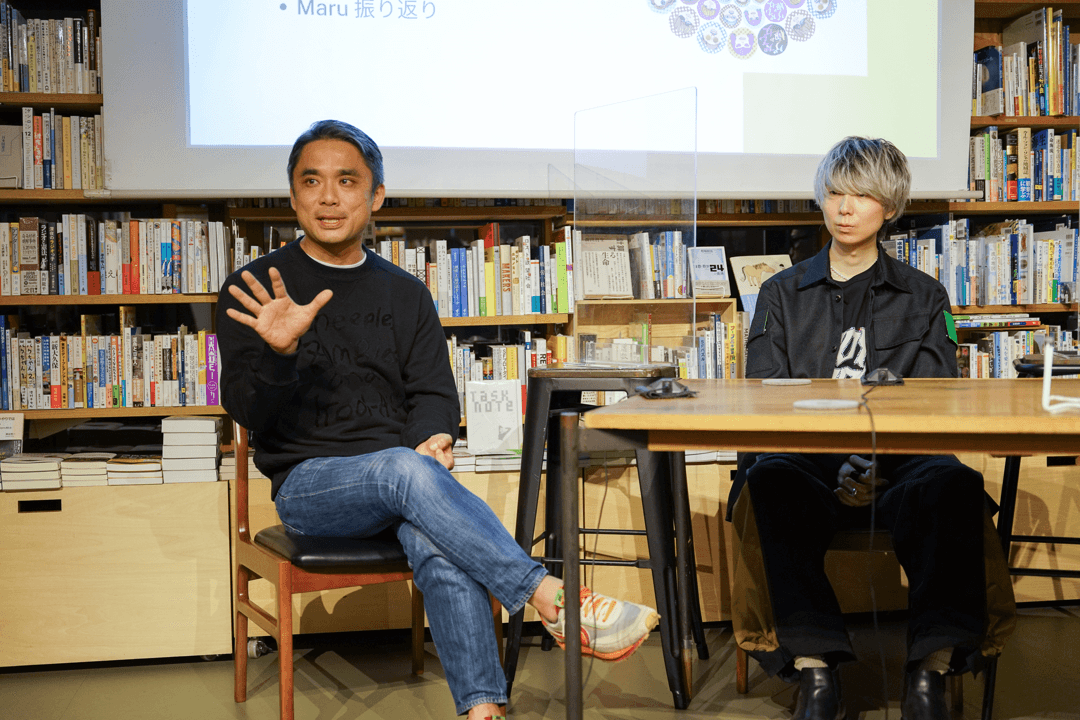
(キャプ)NFTについて語る(左から)岩瀬氏と川谷氏
「Gut Feeling」は世界中の人に聴いてほしい
増井健仁氏(以下、増井):まずは、今回なぜNFT作品を作ることになったのか、教えていただけますか?
川谷絵音氏(以下、川谷):バンド結成10周年のタイミングで、バンド名を「ゲスの極み乙女。」から「ゲスの極み乙女」に改名しました。最後の「。」をなくすことで、終わりなくバンドが続いていくという意味にもなると思ってそうしたのですが、取った「。」で何か面白いことができないかと考える中で、NFTのアイデアが出てきました。
増井:「Gut Feeling」はNFTのために書き下ろした楽曲ということで、曲作りで意識したポイントはありますか?
川谷:ゲスの極み乙女は初期から、ジャズやプログレなど、いろいろな要素を取り入れた複雑な楽曲が多かったんです。今回は、NFTにすることで、日本だけでなく世界中の人に聴いてほしい思いが強かったので、できるだけシンプルに作ろうと意識しました。
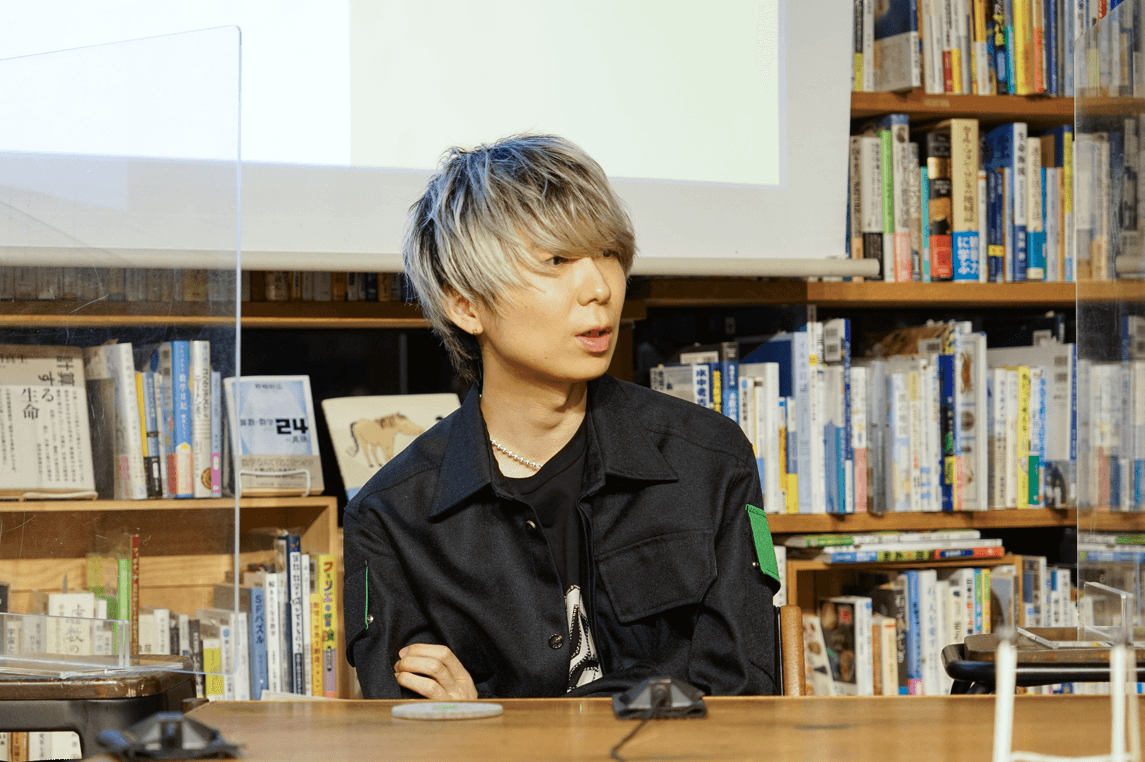
(キャプ)NFTについてはいまも“勉強中”と語る川谷氏
増井:実際のところ、販売したNFTの3割が北米で売れているということで、そういった層にも響いたのかなと感じます。
川谷:海外と日本では音楽の聴き方が違うというか、日本人は歌詞をしっかり聴く人が多いけれど、外国人はリズムで聴く傾向があるので、そこからヒントをもらった部分は大きいですね。
岩瀬大輔氏(以下、岩瀬):今までの音楽業界では、「できるだけ多くの人に聞いてもらう」というのが主流でしたよね。一方で「Gut Feeling」は、当面の間NFTの購入者のみ聴くことができます。せっかく作った楽曲が一部の人にしか聴かれないという点は、どのように感じていましたか?
川谷:そもそも、全部の曲を全員に聴いてほしいとは思っていないのかも。「この曲はこういう人に聴いてほしい。でも好きではない人もいるだろうな」と思いながら曲を出す時もあるわけで。だから今回のように、最初から聴ける人の幅を狭めるというのは、1つの可能性としてありなのではと感じています。
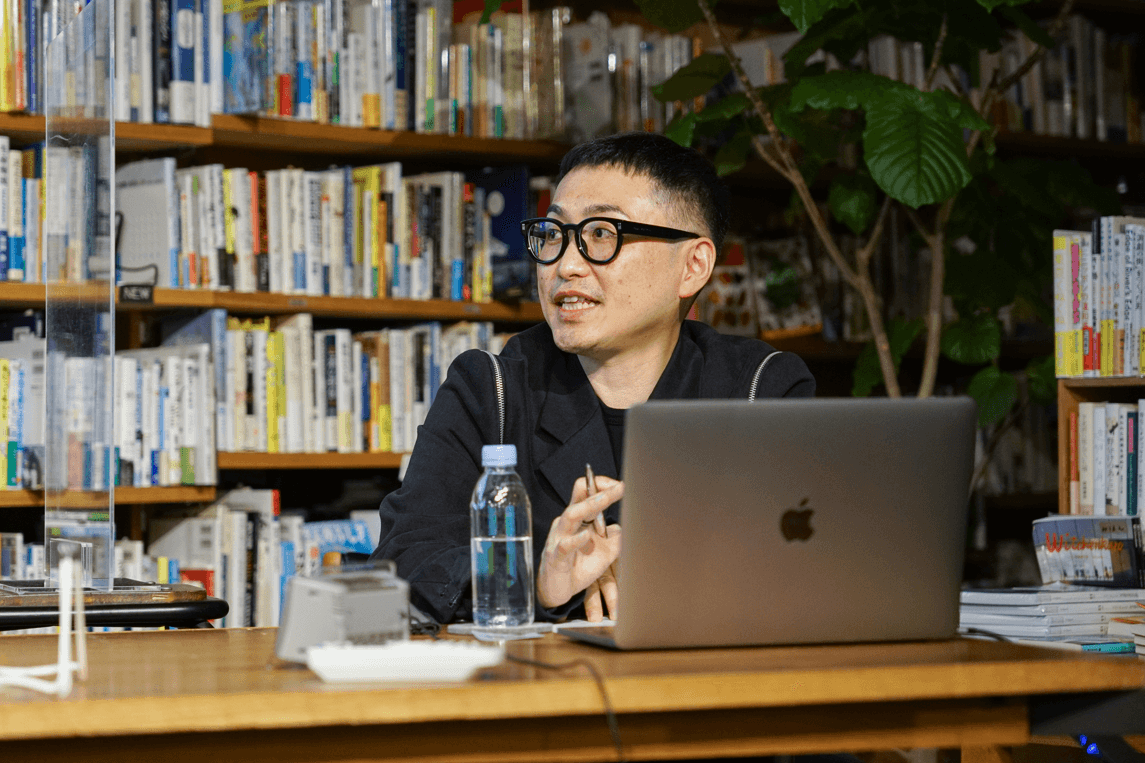
(キャプ)トークライブを進行する増井氏
デジタルが伸びる一方で、アナログが回帰?
増井: 岩瀬さんは「ライフネット生命」の創業者でもありますが、そこからNFTの分野に進もうと思ったのはなぜですか?
岩瀬:私は香港に住んでいるのですが、日本より早く、2020年頃からNFTが一般の人の中で話題に上るようになっていました。もともと金融とテクノロジーが交差する部分には興味がありましたが、NFTによって、そこにアートとグローバルという要素も掛け算できると感じて、NFTの会社を立ち上げました。
増井:改めて、NFTについて簡単にご説明いただけますか?
岩瀬:従来、デジタルのファイルは簡単にコピーや上書きができましたが、NFTはブロックチェーンという技術を使い、ファイルすべてに背番号を付けることで、デジタルのアイテムでも、「これは私のものです」と所有を証明できるようにしました。
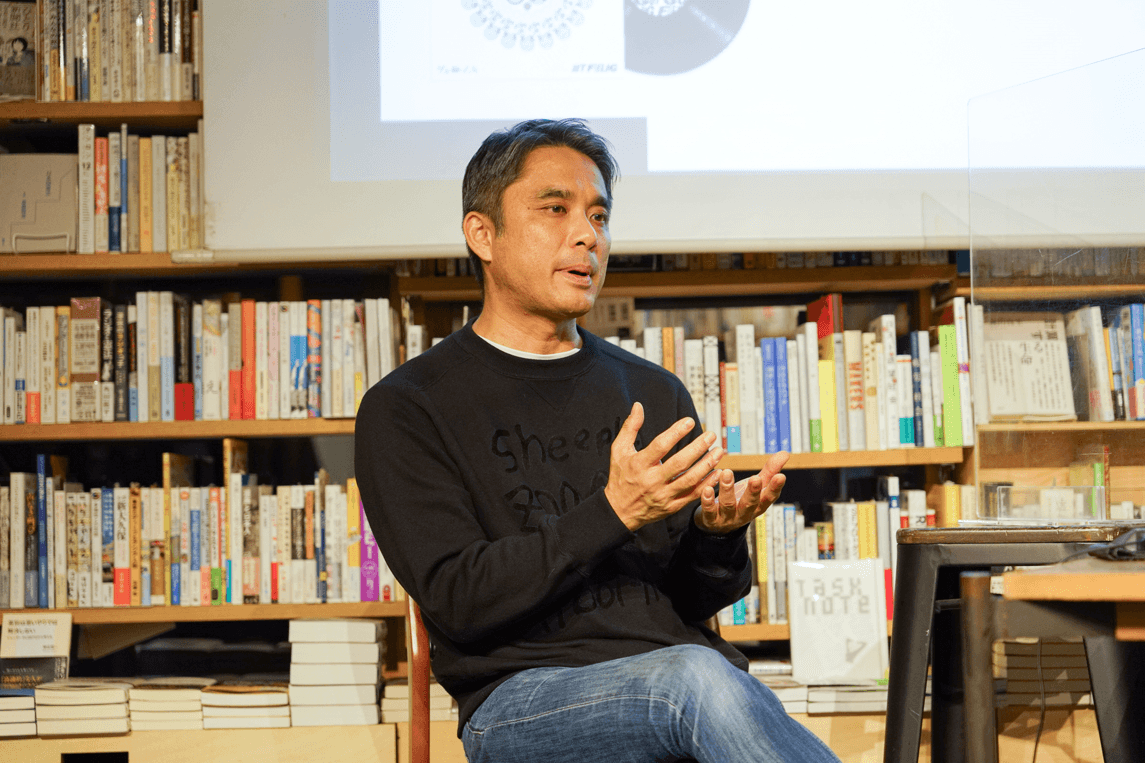
(キャプ)かつては保険、現在はNFTの分野でビジネスをする岩瀬大輔氏
岩瀬:NFTはすでにエンタメの世界にも進出してきていて、例えばスヌープ・ドッグ(アメリカ出身のラッパー)はNFTの楽曲を無料で配布しました。そのデータを自由に使って、誰でも新しい音楽を作ることができます。もう一つの事例として、ザ・ウィークエンド(カナダ出身のシンガーソングライター)の楽曲をプロデュースしたダニーボーイスタイルズは、NFTの購入者が株主のような立ち位置になり、その楽曲が使用されるたびに持分に応じた利益を得られるという仕組みを作りました。
増井:そういった流れの中で、今回川谷さんが挑戦されたのは、「NFT版をとるか、アナログ版をとるか」という投げかけですよね。NFTとして発表された「Maru」は、「。」をさまざまなデザインに展開し、「Gut Feeling」のステム音源が収録された、すべてがオンリーワンの作品です。購入者は、NFTの権利を放棄して1点もののレコードに引き換えることもでき、「NFTのまま所有するかリアル版を入手するか」、どちらか選べるようになっています。このようにした意図をお聞きできますか?

(キャプ)NFTと音楽を掛け合わせた可能性について語る(左から)川谷氏と増井氏
川谷:今はサブスク全盛期ですが、一方でカセットテープが注目を集めていたり、レコード人気が再燃していたりします。きっとこれからもデジタルはもっと伸びていくでしょうが、その反動でアナログに戻る動きもある。そんな風に、デジタル・アナログという矛盾したものが同時に伸びているというのがおもしろかったので、その矛盾をつなぐようなことができればと思いました。
増井:なるほど。岩瀬さんにお聞きしたいのですが、NFTを一般化させていくうえで、目の前にあるハードルとしては何があるとお考えですか?
岩瀬:やはり、デジタルのものにお金を払い所有するということに慣れていない点が大きいかなと。ただ、圧倒的なメリットがあれば受け入れられるはずなので、NFTにしかない価値を工夫して作っていかなければならないと思います。
増井:川谷さんは、NFTにどのような可能性を感じていますか?
川谷:「NFT音楽作品のサブスク」のようなサービスができるのではと思います。購入したデータをNFTとして所有し続けるか、アナログ版に引き換えるかを当たり前に選べる。そういった新しいプラットフォームも可能なのかなと。自分としては、良い曲を作りながら、バンドメンバーと一緒に、自分たちがおもしろいと感じられることをやり続けていきたいです。
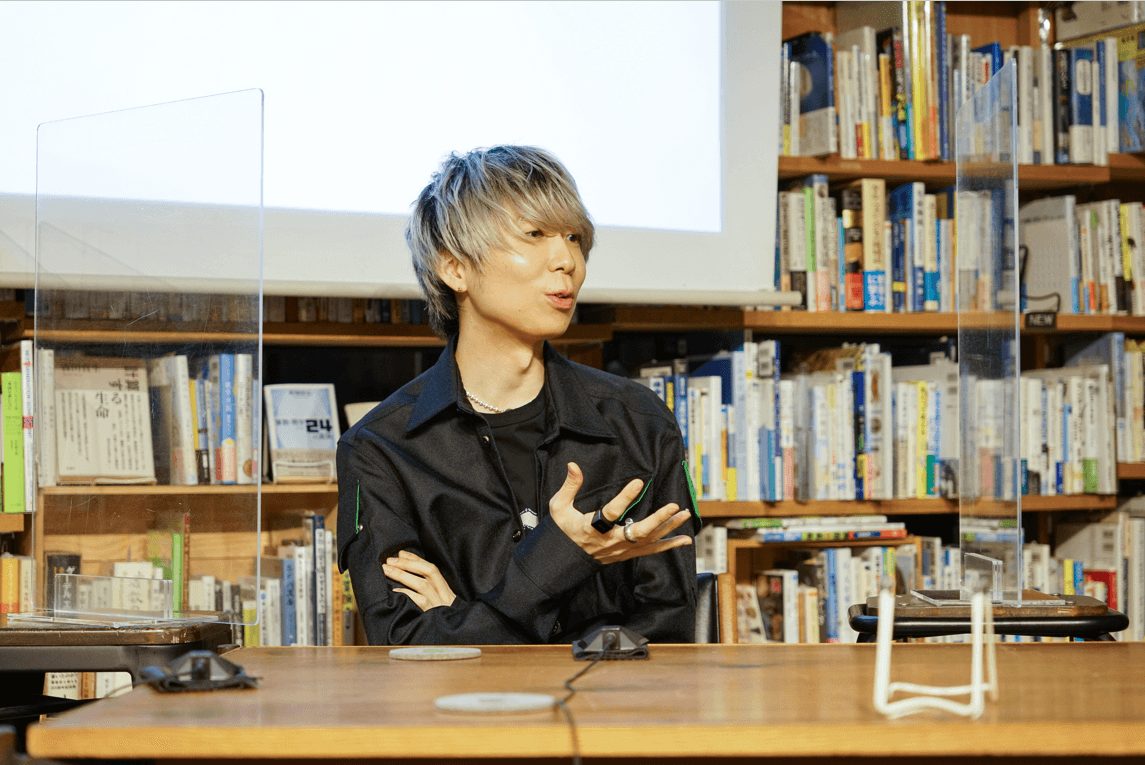
(キャプ)音楽業界の未来を語る川谷氏
今後NFTかアナログかの選択がもたらす価値は?
このように、NFTの可能性、ひいては音楽業界の可能性について熱く語られたトークライブは1時間にわたり開催され、興奮冷めやらぬまま幕を閉じました。今回のゲスの極み乙女、KLKTN、ワーナーミュージック・ジャパンの3者による壮大なプロジェクトが、今後の音楽業界の指針になる可能性を秘めていることを会場にいた誰もが気づいたことでしょう。
NFTを購入し、アナログ版に引き換えるか否か自ら選択するという“新体験”。今後どのような形で音楽とNFTに新しい価値をもたらしていくのか、音楽業界にいる人はもちろん、ファンにとっても期待は膨らむばかりです。













